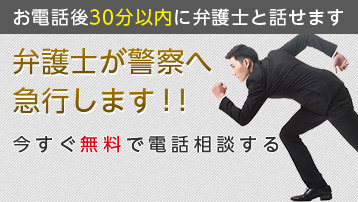飲酒検問で呼気検査を拒否したらどうなる? 問われる罪と逮捕される可能性
- 交通事故・交通違反
- 呼気検査
- 拒否

令和3年6月、千葉県八街市において飲酒運転のトラックが下校中の小学生の列に突っ込み、児童2人が死亡、3人が大けがをした事故が発生しました。
このような痛ましい飲酒運転の事故をなくすため、飲酒機会が増える時期に、警察は取り締まりをして呼気検査を行っています。一方で、呼気検査を要求されることに納得がいかず、拒否するという方もいるようです。
しかしながら、呼気検査を拒否するだけで「飲酒検知拒否罪」という罪に問われる可能性があります。本コラムでは、呼気検査を拒否すると逮捕される可能性がある理由や逮捕後の流れについて、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士が解説します。


1、呼気検査とは?
アルコールは人間の判断能力に影響を及ぼすため、道路交通法第65条において「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と定められています。
原則として「一滴でも飲んだら乗るな」ということです。
アルコールを経口摂取した後の呼気には、一定時間はアルコールが含まれます。呼気に含まれるアルコール量は、アルコールに強い弱いという体質に左右されることはありません。
客観的な数値で判断できるため、警察は、主に呼気検査によって飲酒運転を取り締まります。
-
(1)呼気検査を拒否すると、現行犯逮捕の可能性も
ドライバーが酒気帯び運転するのを防止するため、道路交通法第67条3項において、警察官に呼気検査をすることを認めています。
また、罰則は以下の通りです。
罰則
第67条(危険防止の措置)第3項の規定による警察官の検査を拒み、または妨げた者は、3か月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
(道路交通法118条の2項)
ドライバーからアルコールの臭いがしたと感じ、呼気検査の要請を行ったものの、ドライバーが応じず拒否する場合は、警察官が「飲酒検知拒否」の現行犯逮捕に踏み切るケースもあります。
-
(2)呼気検査の拒否だけで逮捕される理由
果たして検査拒否だけで逮捕されるのか疑問に思う方もいるかもしれません。
しかし酒酔い運転による死亡事故が後を絶たない現状で、検査を免れ逃走を許せば、危険運転で一般市民を危険にさらすこととなります。
そもそも、何らかの罪を犯した被疑者を逮捕することができるのは、原則として「証拠隠滅や逃亡のおそれがある」ときに限られています。
飲酒運転は、時間経過によって体内のアルコールが分解されることにより物的証拠が取りにくくなるため、時間稼ぎはそのまま「証拠隠滅」につながるといえるでしょう。
つまり呼気検査拒否は、まさに飲酒運転の罪を疑われていながら「逃亡のおそれがある」といえる状況です。警察官の要請に応じないと、逮捕に踏み切られる可能性は大いにあると考えた方がよいでしょう。
2、呼気検査で摘発する道路交通法違反行為とその罰則
飲酒運転は、「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」に分けられます。
それぞれ罰金等の刑事処分と、行政処分として運転免許に違反点数が付されます。
-
(1)酒気帯び運転
呼気1リットルあたり0.15mg以上のアルコールを含んでいる状態で車を運転すると、体内に一定量のアルコールを保有した状態とされ「酒気帯び運転」として処罰されます。
罰則
「3年以下の懲役」または「50万円以下の罰金」と定められています。
(道路交通法第117条の2の2第3号)
なお、行政処分として、違反点数は13点、免許停止90日間となります。
呼気アルコール濃度が0.25mgを超えている場合の違反点数は25点、免許取り消しとなり欠格期間は2年です(その間、免許の交付が受けられません)。 -
(2)酒酔い運転
呼気のアルコール濃度に関係なく、アルコールの影響で正常に運転できない状態で車を運転すると処罰されます。会話が正常に成り立たない、ろれつが回らない、まっすぐ歩行できずふらつくなどの様子があれば、酒酔い運転と判断されるでしょう。
酒に酔った状態で運転するのは危険行為であり、酒気帯び運転よりも量刑は重くなります。罰則
「5年以下の懲役」または「100万円以下の罰金刑」と定められています。
(道路交通法第117条の2第1号)
行政処分は、違反点数35点、免許取り消しのうえ、欠格期間は3年です。
アルコールに弱い人であれば、呼気1リットルあたりのアルコールが0.15mg未満であっても酒酔い運転と判断されるケースがあります。
お問い合わせください。
3、逮捕された後の流れ・裁判について
飲酒運転や呼気検査拒否による逮捕は、主に現行犯逮捕となるでしょう。
逮捕された後は、以下のような流れで手続きが進められていきます。
-
(1)警察での取り調べ
逮捕されてから48時間以内は警察での取り調べを受けます。
原則として、逮捕直後は家族でも面会することはできませんが、弁護士であれば、被疑者といつでも接見することができます。
罪が軽微な場合は「微罪処分」といい、警察官の厳重注意のみで刑事責任は問われず身柄が解放されるケースもあります。 -
(2)送致
警察は逮捕後48時間以内に、検察に送致するか判断します。
身柄ごと送致する場合と、身柄を解放して事件の調査書類のみを検察に送致する場合があります。後者は在宅事件扱いといい、報道で書類送検と報じられるケースです。 -
(3)検察での取り調べ・勾留
検察へ移送された後、検察官は引き続き身柄を拘束して取り調べる「勾留(こうりゅう)請求」をするか、釈放するかを24時間以内に決定します。
裁判所から勾留の許可が下されたらまず10日間以内、延長が認められると最長20日間にわたって取り調べが行われ、検察はその間に起訴するかどうか判断します。 -
(4)刑事裁判で有罪となれば前科がつく
不起訴処分となった場合は釈放され、前科がつくことはありません。
起訴の場合は、刑事裁判の手続きへと移行します。
飲酒運転で事故を起こし、人を死傷させた場合は「危険運転致死傷罪」などに問われ、刑事裁判となるケースもあるでしょう。裁判の期間は長いと1年ほどかかるケースもあります。
また、100万円以下の罰金刑が見込まれる場合は、「略式起訴」になるケースもあります。
この場合、書類手続きのみの裁判となり、裁判官が法定刑の範囲内で罰金を決めて、判決にあたる「略式命令」を下します。前科はつきますが、略式起訴が行われたら即日釈放されます。
その後、略式命令の期日以内に罰金を支払ったらすべての手続きは完了します。
4、飲酒運転で逮捕されたら弁護士に相談すべき理由
自身やご家族が飲酒運転で逮捕された場合は、次の理由から早急に弁護士へ相談しましょう。
-
(1)弁護士であれば、いつでも何回でも接見できる
万が一逮捕された場合、もしくはされそうなときは、すぐに弁護士に依頼してください。ご家族からの連絡でも問題ありません。
なぜなら、逮捕後は家族であっても面会できません。勾留の有無が決定するまでの最長3日間、外部と連絡を取ることが制限されます。
つまり、自分で仕事や学校を休むなどの連絡をすることもできなくなるのです。
しかしながら、弁護士であればいつでも、何回でも接見できます。家族との連絡を仲介することもできるでしょう。 -
(2)取り調べの対応についてアドバイスができる
接見を行った際、状況を聞いたうえで取り調べの応じ方のアドバイスをすることができます。早く釈放されたいがために、事実と反した供述をしてしまうと、のちのちやってもいない罪に問われてしまう展開になる可能性があります。
弁護士のサポートの有無は、その後の結果に大きく影響するでしょう。 -
(3)身柄の早期解放のために活動を行える
逮捕されて取り調べを受けた時点で「前歴」はつきます。
しかし、前歴は履歴書などに記載する必要はありませんし、将来への影響はほとんどないでしょう。
問題は、実際に処罰を受けたときにつく「前科」です。
弁護士に依頼することで、前科がつかない「微罪処分」や、不起訴処分になるよう働きかけ、身柄の早期解放のために活動します。
具体的には、事故などで被害者がいる場合は、示談成立を目指し交渉を行います。早期に示談が成立していれば、勾留に至らず釈放されたり、不起訴処分になったりする可能性が高まります。
検察に送致された場合も、不起訴処分またはなるべく軽い量刑となるように、反省の意を伝えたり、意見書を作成したりしてあなたの将来への影響を最小限とするように弁護活動を行います。
起訴事実を争わず略式起訴を受け入れるべきかなど、どのような策か最善なのか、弁護士と相談することができれば心強いでしょう。 -
(4)裁判になった場合の弁護活動もできる
裁判となれば、当然に弁護士の助けは必須となるでしょう。
裁判で必要になる証拠収集や刑の軽減のために弁護活動を行います。無実を主張する場合においても、そのためにさまざまな準備や知識が必要です。
逮捕後身動きがとれないあなたに代わって、あなたの権利を守ります。
お問い合わせください。
5、まとめ
急いでいるときに、検問で警察官から呼気検査を要求されると、むっとしてしまうことがあるかもしれません。
しかし、呼気検査を拒否すると、道路交通法違反で処罰されてしまう可能性があります。
警察官から呼気検査を要求されたら、素直に従うのが得策です。万が一、呼気検査を拒否して警察とトラブルになった場合は、早い段階で弁護士に相談しましょう。
道路交通法に関するトラブルや事故、示談でお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスまでご相談ください。
刑事事件や交通事故の対応経験豊富な弁護士が、適切な対応をご提案します。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|