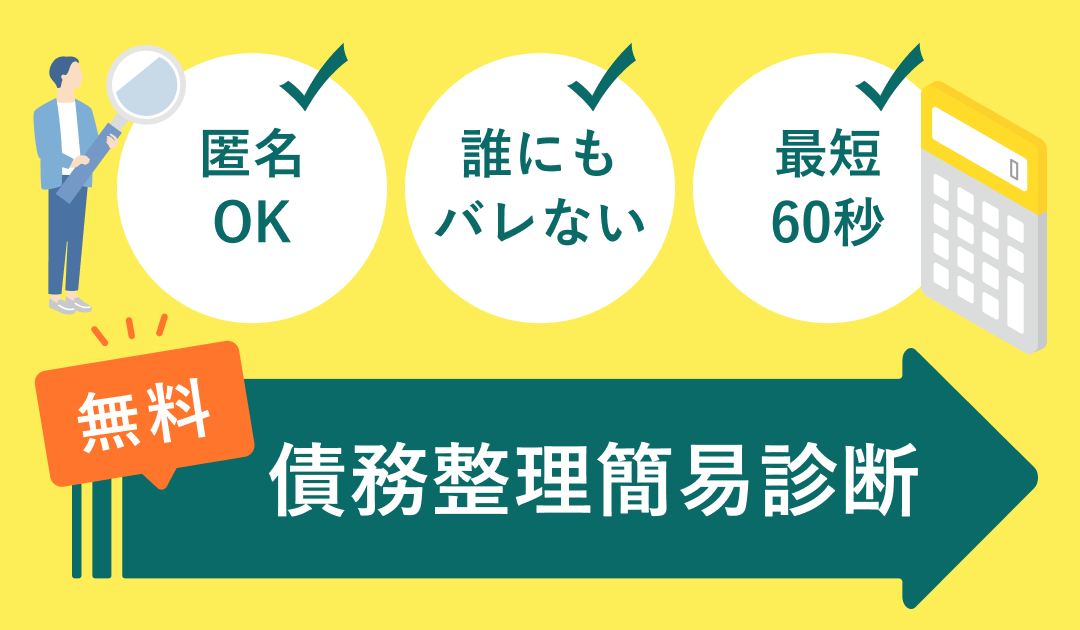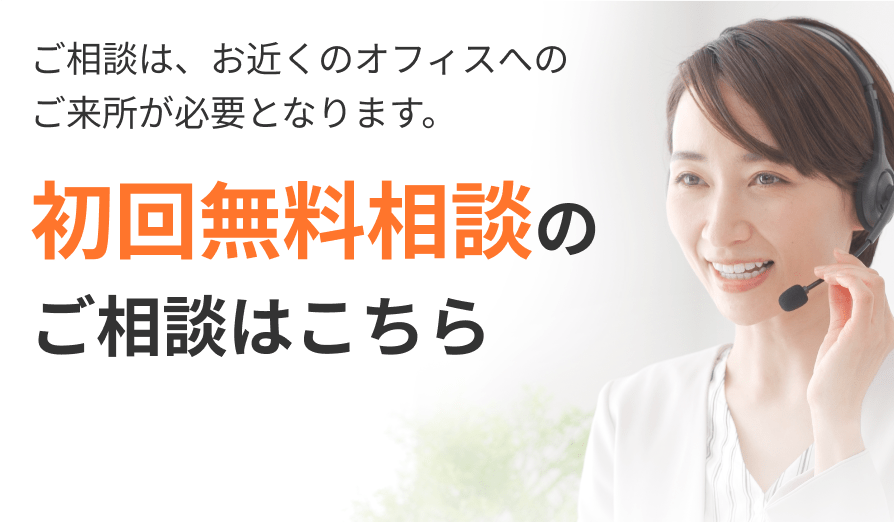残余財産の分配方法は? 会社の清算完了までの手続きの進め方を解説
- その他
- 残余財産の分配

帝国データバンクの調査によると、2020年中の千葉県内における企業の休廃業・解散件数は1984件で、前年比4.4%の減少となりました。
会社を解散・清算する場合、手続きの中で株主に「残余財産の分配」を行います。残余財産の分配を含めて、会社清算の際には順次段階を踏んで手続きを行う必要があるので、弁護士に相談のうえ適切に対応してください。
この記事では、残余財産の分配を含めた会社清算の流れについて、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士が解説します。
出典:「千葉県内の「休廃業・解散」動向調査(2020年)」(帝国データバンク)
1、会社の残余財産とは?
「残余財産」とは、会社を解散・清算する際に、債権者に対して債務の支払いを行った後に残った資産のことです。
株式会社の実質的な所有者は、会社に対して出資を行っている「株主」です。
したがって、株主は残余財産分配請求権を有するため、残余財産は最終的に株主に対して分配されます。
残余財産の分配は、株式数に応じて行われるのが原則ですが、株式ごとに異なる定めをすることもできます(種類株式。会社法第108条第1項第2号)。
なお、合名会社・合資会社・合同会社においても、会社を解散・清算する際には、社員(持分権者)に対して残余財産の分配が行われます。
ただし、これら持分会社の場合には、株式会社に比べて、残余財産の分配手続きが簡素化されている点が特徴的です。
また、持分会社においては、清算手続きに関する会社法の規定にかかわらず、清算方法を定款または総社員の同意によって定めることも認められています(任意清算。会社法第668条以下)。
※本記事では、任意清算に関する解説は割愛します。
2、会社の残余財産を分配する前に必要な手続きは?
会社の残余財産の分配は、解散・清算手続きの一環として行われます。
残余財産の分配が行われるのは、解散・清算手続きの中でも終盤の段階です。
そこで、まずは残余財産を分配する前に必要となる手続きを順次見ていきましょう。
-
(1)会社の解散を決定する
まずは会社の解散について、株主総会で特別決議※を経る必要があります(会社法第471条第3号)。
特別決議の要件(会社法第309条第2項)
① 行使可能議決権の過半数を有する株主の出席(3分の1以上の割合を定款で定めた場合には、その割合以上の株主の出席)
② 出席株主が有する議決権の3分の2以上の賛成(これを上回る割合を定款で定めた場合には、その割合以上の賛成)
なお、清算手続きが結了するまでの間は、再度株主総会特別決議を経ることによって、解散を撤回して株式会社を存続させることが可能です(会社法第473条)。
これに対して持分会社の場合、会社の解散を決定するためには、総社員の同意が必要とされています(会社法第641条第3号)。 -
(2)清算人が現務を結了する
会社の解散が決定された場合、同時に清算手続きが開始されます(会社法第475条第1号、第644条第1号)。
清算会社(清算株式会社・清算持分会社)には「清算人」が設置され(会社法第477条第1項、第646条)、会社を代表して清算手続きに関する職務を行います。
清算株式会社の場合、清算人となるのは、基本的に取締役です(会社法第478条第1項第第1号)。
これに対して、清算持分会社の場合は、業務執行社員が清算人となります(会社法第647条第1項第1号)。
就任した清算人は、まず現務を結了する必要があります(会社法第481条第1号、第649条第1号)。
たとえば、取引先との継続的契約を解約したり、従業員との労働契約を解消したりすることが「現務の結了」に該当します。 -
(3)財産目録・貸借対照表の作成等を行う
現務の結了と並行して、清算人は就任後遅滞なく、財産目録および貸借対照表の作成を行う必要があります(会社法第492条第1項、第658条第1項)。
株式会社の場合、財産目録および貸借対照表の作成について公正を期す必要があるため、株主総会の承認(会社法第492条第3項)を受ける必要があります。
さらに貸借対照表については、監査役の監査(会社法第495条第1項、監査役設置会社の場合)および清算人会の承認(同条第2項、清算人会設置会社の場合)も必要です。
一方、持分会社の場合は、財産目録および貸借対照表を作成した後に、各社員にその内容を通知することで足ります(会社法第658条第1項)。 -
(4)債権の取り立てと債務の弁済を行う
清算人は、残余財産の分配に先立って、清算会社が有する債権の取り立てと、清算会社が負っている債務の弁済を行います(会社法第481条第2号、第649条第2号)。
債権の取り立ては、清算人の判断により、適切な方法を用いて行えば足ります。
これに対して、債務の弁済については、以下の流れに従って行う必要があります。債務の弁済の流れ
① 弁済申出の公告・個別の催告
会社が解散した場合、会社はその後遅滞なく、債権者に対して一定期間内に債権を申し出るべき旨を公告しなければなりません(会社法第499条第1項、第660条第1項)。
公告期間は、2か月以上に設定する必要があります。
また、会社にとって知れている債権者に対しては、債権申出を個別に催告する必要があります。
② 弁済
公告期間中に弁済申出がなされた債務について、それぞれ弁済を行います。
なお、公告期間中に申出がなかった債権については、清算手続きから除斥され、残余財産の分配後に弁済を受けられるにとどまります(会社法第503条第1項、第2項、第665条第1項、第2項)。
お問い合わせください。
3、会社の残余財産を分配する際の流れは?
清算人の業務が債務の弁済まで完了したら、株主(社員)に対して残余財産の分配を行います。
株式会社と持分会社では手続きが大きく異なるので、それぞれの場合に分けて手続きの流れを解説します。
-
(1)株式会社における残余財産の分配手続き
清算株式会社では、以下の流れに従って残余財産の分配を行います。
① 残余財産の分配に関する事項を決定する|現物分配も可
清算株式会社が残余財産の分配をするには、清算人の決定(清算人会設置会社では、清算人会の決議)によって以下の事項を定める必要があります(会社法第504条第1項)。- 残余財産の種類
- 株主に対する残余財産の割り当てに関する事項
なお、残余財産を金銭以外の財産とすることも可能です(現物分配。会社法第505条第1項)。
ただし、現物分配が行われる場合にも、株主は会社に対して金銭分配を請求することが認められます(会社法第505条第1項)。
② 決定内容に従って残余財産を分配する
上記の決定内容に従って、実際に株主に対して残余財産を分配します。 -
(2)持分会社における残余財産の分配手続き
一方、清算持分会社においては、残余財産の分配方法について、会社法上詳細なルールは定められていません。
唯一設けられている会社法第666条では、まず定款の定めに従い、定款の定めがない場合には社員の出資割合に応じて残余財産を分配する旨が定められています。
したがって、清算人が裁量的に残余財産を分配し、最終的な総社員の同意を取得するという流れになります。
4、残余財産を分配した後、清算完了までの流れは?
残余財産の分配が完了したら、清算手続きは仕上げの段階に入ります。
残余財産の分配後、清算完了までには以下の手続きをとることが必要です。
-
(1)決算報告の作成(計算)・株主総会(社員)による承認
清算事務が終了した場合、精算株式会社は遅滞なく決算報告を作成しなければなりません(会社法第507条第1項)。
一方、清算持分会社の場合には、決算報告の形式を整える必要はなく、精算に係る計算を行うことで足ります(会社法第667条第1項)。
決算報告(計算)の内容については、株主総会(清算持分会社では、社員)の承認を受けることが必要です(会社法第507条第3項、第667条第1項)。
かかる承認を受けた段階で、会社の清算は結了し、会社の法人格は消滅します。 -
(2)清算結了の登記
会社の清算が結了した場合、決算報告(計算)の承認日から2週間以内に、本店所在地において清算結了の登記をしなければなりません(会社法第929条)。
-
(3)清算人による帳簿資料の保存
清算株式会社では、清算結了の登記の時から10年間、清算人が以下の資料を保存しなければなりません(会社法第508条第1項)。なお、清算人に代わる保存者が選任されることもあります(同条第2項)。
- 清算株式会社の帳簿
- 清算株式会社の事業および清算に関する重要な資料
清算持分会社の場合も同様です(会社法第672条。)
お問い合わせください。
5、まとめ
会社の清算を行う場合、残余財産の分配を含む多段階の手続きを経る必要があり、複雑な対応に多大なる労力を要します。
そのため、会社を清算する必要が生じた場合には、弁護士にご相談のうえで対応することをおすすめします。
ベリーベスト法律事務所では、企業法務を専門的に取り扱うチームが、円滑に清算手続きを完了できるようにサポートいたします。
会社の休廃業をご検討中の経営者の方や、会社の清算手続きについてご不明点やご不安をお抱えの方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスにご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています