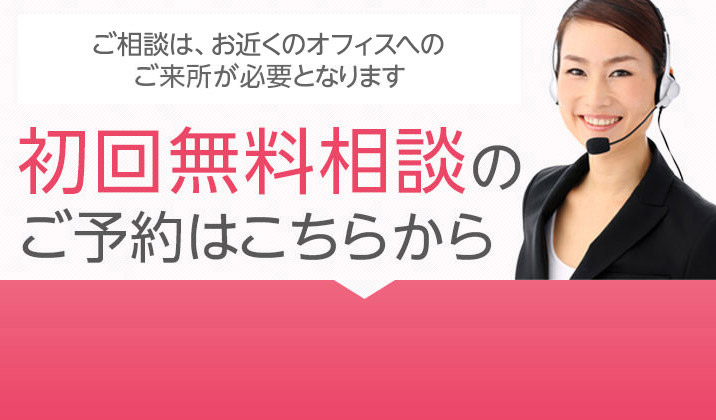年収1000万の夫と離婚…養育費の相場はいくら?養育費を貰うための対策
- 離婚
- 年収1000万
- 養育費
- 相場
- 弁護士

千葉県の統計によると令和5年中の離婚件数は9151件で、約57分に1組が離婚していることになります。離婚の際はさまざまなお金のやり取りが発生しますが、中でもトラブルになりやすいのが養育費です。
養育費は父母の年収や子どもの人数・年齢などによって増減するため、相手の年収が高ければ受け取る養育費も高額になります。しかし、養育費を支払わない方が多いため、受け取れている世帯は非常に少ない傾向です。
本コラムでは、親権がない側が年収1000万円のケースにおける養育費の相場や、養育費を受け取るためにすべき対策について、ベリーベスト法律事務所 千葉オフィスの弁護士が解説します。


1、年収1000万の場合の養育費の相場(新養育費算定表による相場)
ここでは、母親が子どもの親権を持ち、父親が養育費を支払うという前提で算出しています。なお、養育費の支払いに男女差はないため、立場を逆にして読み替えても問題ありません。
養育費は子どもの人数等によって異なるため、自身の状況に合致するものを参考にしてください。
例1:父親がサラリーマンで年収1000万円・母親が専業主婦で無収入の場合
- 子ども1人(14歳以下)の場合:12~14万
- 子ども1人(15歳以上)の場合:14~16万
- 子ども2人(どちらも14歳以下)の場合:18~20万
- 子ども2人(どちらも15歳以上)の場合:20~22万
- 子ども2人(14歳以下、15歳以上1人ずつ)の場合:18~20万
例2:父親がサラリーマンで年収1000万円・母親が年収300万円の場合
- 子ども1人(14歳以下)の場合:8~10万
- 子ども1人(15歳以上)の場合:10~12万
- 子ども2人(どちらも14歳以下)の場合:約14万
- 子ども2人(どちらも15歳以上)の場合:約16万
- 子ども2人(14歳以下、15歳以上1人ずつ)の場合:14~16万
上記は、あくまで一例です。
ご自身のケースで知りたい場合には、こちらの「養育費計算ツール」が便利です。
無料で、簡単に養育費の試算ができますので、ぜひお試しください。
>養育費計算ツールはこちら
2、養育費の相場と決め方
養育費は、子どもの養育のために支払われるお金であるため、子どもがいない世帯では養育費は発生しません。
養育費は夫婦の話し合いで合意できれば大きな問題とはなりませんが、離婚の際は冷静な話し合いをすることが難しいものです。双方が異なる主張をすることが少なくなく、話し合いが困難になることが多い傾向にあります。
裁判所は「算定表」と呼ばれる、養育費算定の基準となる数値を公表しております。
調停や訴訟ではこちらの算定表の金額を基準にして、養育費は決められることになります。
算定表では、養育費を各家庭の経済状況や子どもの人数によって画一的に決定すべく、以下の3つの状況によって養育費が増減するようになっています。
- ①子どもの人数
- ②それぞれの子どもの年齢
- ③父母それぞれの年収・所得
基本的には、子どもの人数が多い場合や子どもの年齢が高い場合、養育費を支払う側の年収が高い場合は養育費も高くなります。
また、最終的にはそのほかの事情も考慮して決定することになるため、算定表通りの金額を受け取れないケースもあることを知っておきましょう。
3、養育費に関して話し合うべき項目
養育費については金額以外に、以下の項目を離婚前に話し合っておく必要があります。
話し合いで合意できなければ、離婚調停もしくは養育費請求調停などを通じて、調停員に仲介してもらい解決を図りましょう。
解決してから離婚をした方が、その後のトラブルにつながりにくいと考えられます。
-
(1)養育費の支払い方法
まずは、養育費の支払いを一括にするのか分割にするのかを決めておきます。
一般的には分割での支払になりますが、一括で支払える資産が相手にあれば、一括払いにしておくこともひとつの手です。分割払いにする場合は、何日に支払うのか、振込口座はどこにするのか、などの細かい条件も決めておきましょう。 -
(2)何歳まで支払うのか
養育費の支払いは、一般的には子どもが成人するまで、もしくは大学卒業までとする場合が多いでしょう。親としてどうすべきか、あらかじめ話し合っておきましょう。
-
(3)失業や病気などの場合どうするのか
養育費を支払う側が病気や失業などで、収入が減ってしまった場合の養育費の取り扱いにおいてもあらかじめ決めておくと安心です。経済状況が変わった場合には、後から養育費を減額するケースもあります。
-
(4)公正証書の作成
養育費を確実に受け取るために有効なのが「公正証書」です。
公正証書とは、公証役場で作成する書類のことで、公証人が作成し、原本は公証人役場に保管されます。
養育費を約束通り支払わない場合は直ちに強制執行されても異議は唱えないという、強制執行認諾文言をあらかじめ入れた公正証書を作成することによって、記載された支払約束が履行されなかった場合に、裁判などの手続きを経ず強制執行が可能となります。
万が一に備えることができるだけでなく、未払いの抑止力にもなるでしょう。
4、養育費の不払いや滞納への対処法
次に、養育費の不払いや滞納があった場合の対処法について解説します。
-
(1)債務名義がある場合は給与等の差し押さえを申し立てる
「債務名義」がある場合は、裁判所に給与等の差し押さえを申し立てます。
債務名義とは判決文、調停調書、強制執行認諾文言のある公正証書などです。
債務名義がある場合は、相手の住所地を管轄する地方裁判所に「債権差押命令」を申し立てます。債権差押命令の申し立てには、強制執行認諾文言のある公正証書などの債務名義と執行文、送達証明書という書類が必要です。なお、債務名義の種類によって必要な書類は変わるため確認が必要です。
協議離婚で離婚協議書を作成したものの公正証書にしていなかったり、公正証書にしていても強制執行認諾文言がなかったりすれば債務名義はないため、次項で解説する調停を申し立てます。 -
(2)債務名義がない場合は調停を申し立てる
まずは電話やメールなどで連絡を取りましょう。相手が電話に出ない、支払いに応じない、などの場合は内容証明郵便を送付し支払いを促します。
内容証明自体には法的な拘束力はなく、支払いを強制することはできませんが、心理的なプレッシャーを与えることは可能です。
それでも支払われず、債務名義がなければ、裁判所に調停を申し立てなければなりません。調停は、養育費の金額や支払い方法などを話し合うものです。
調停で養育費の支払いに合意すれば調停証書が作成され、債務名義を取得可能です。
なお、調停や裁判手続きは、家庭裁判所にて行われます。千葉県内の主な家庭裁判所は以下です。詳細や最新情報は、裁判所ホームページをご確認ください。
裁判所ウェブサイト(管内の裁判所の所在地)
■千葉家庭裁判所
〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4-11-27
支部:佐倉、一宮、松戸、木更津、館山、八日市場、佐原
出張所:市川 -
(3)弁護士に依頼する
これから離婚をする方、養育費についての話し合いがうまくいかない方は弁護士に一度相談しましょう。養育費の相場を把握した上で、相手に請求できる方法や相手からの支払が遅延した場合の対策などについてアドバイスしてもらえます。
すでに養育費の支払いが遅延している場合は、早急に対策を講じなければなりません。遅延金額が増えれば増えるほど、相手の支払いも困難となり、取り立てが難しくなります。
弁護士であれば、裁判所の申し立ての手続きもスムーズに着手可能です。
5、養育費が減額になるパターンと対処法
養育費の支払金額は、養育費を支払う側の生活などが変化した場合に減額が認められるケースがあります。
ここでは、養育費が減額されるパターンと、回避方法を解説します。
-
(1)養育費が減額になるパターン
養育費を支払う側に以下のような変化があった場合は、養育費の減額が認められてしまう可能性があります。
①リストラ、失業、減給、病気や事故など
養育費を決定したときよりも収入が減った、無収入になったなどの場合はそれまでと同額の養育費を支払うことは困難となるため、減額されてしまう可能性があります。
②支払う側が再婚し、子どもが生まれた
養育費を支払う側が再婚して、子どもが生まれ養育すべき家族ができた場合は、養育費の減額を請求されることがあります。
③受け取り側の収入が増えた
離婚後に、養育費を受け取る方の収入が増えると、減額が認められる可能性があります。 -
(2)養育費の減額請求を回避する方法は?
養育費は、一方的な主張で減額が認められる訳ではありません。
先方から養育費の減額を求められたら、拒否をしてもよいでしょう。
それでも相手が減額を求める場合は、相手が養育費減額請求調停を起こすことになります。調停を通じて減額が妥当であると認められれば、減額されてしまいます。
減額されすぎないようにするためにも、弁護士に交渉を委任することをおすすめします。
弁護士であれば、客観的証拠をもとに、養育費を減額されたら生活が成り立たないことなどを主張することで、減額請求を回避できる可能性が高まります。
お問い合わせください。
6、まとめ
養育費は、子どもが親と同等の文化的かつ健康的な生活を送るために必要な費用です。
もし協議離婚をするのであれば、離婚前にきちんと支払金額や支払い方法などを取り決めて公正証書にしておくことで、養育費の未払いを予防できます。
すでに未払い状態になっている場合は、弁護士に相談のうえ、調停を申し立てることになります。
現在、離婚の養育費で悩んでいる方、不払いで困っている方はベリーベスト法律事務所 千葉オフィスにご相談ください。養育費の金額の取り決めや離婚問題全般について、きちんとお話を伺った上で、あなたの代理人として請求などの対応を行います。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています